足利氏、新田氏のプロフィール 参・鎌倉時代の両氏の動き
1.北条政権下における足利義氏の活躍
鎌倉において、頼朝と同族の清和源氏出身では、筆頭の家格を占めた足利氏であるが、政権の担い手が頼朝直系から北条氏に移ろっていく際には、積極的に北条氏に同心し、幕府内部にて自らの地位を固めていった。
以下に、鎌倉時代における足利の系図を示す。
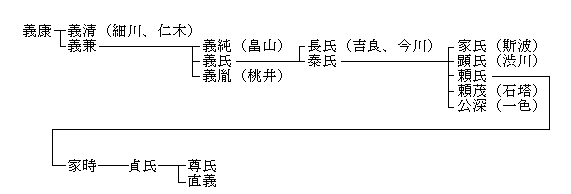
義兼の跡を受けて足利宗家を継いだ義氏は、初代執権北条時政の甥にあたり、母の生家(北条)に一貫して協力し続けた。頼朝没後の権力争いで、名門御家人和田義盛と北条方が衝突した和田合戦(1213)では、和田氏の勇将朝比奈義秀と激戦を演じて武名を大いに上げた。
その後、検非違使、武蔵守、陸奥守、左馬頭を歴任。従四位に叙せられ、北条政権下での源氏筆頭として、その地位を確固たるものにする。
後鳥羽上皇が朝廷の兵を率いて鎌倉に挑んだ承久の乱(1221)、北条方が名門御家人三浦氏を挑発して合戦を仕掛けた宝治合戦(1247)などでも常に北条の主戦力として活躍した。(←はい、ここ注目。大河ドラマ「北条時宗」と史実は違ってますな。先代義氏、いまだ健在。この時点では足利氏と北条氏の対立もありえない。というか、足利と北条の蜜月期やがな。)この間、義氏は三河守護に補任、承久の乱の恩賞として美作国を、宝治合戦では千葉秀胤の所領を没収して上総国を支配下に収め、鎌倉時代の足利氏全盛を築いた。
足利各分家の繁栄も、この時期義氏が獲得した所領に負う所が大きい。
2.鎌倉方の冷遇を受ける新田氏
本来、源義国の嫡男で、足利の上に立つべき家系ながら、鎌倉方の覚えがめでたくない新田氏は、さらに迷走が続く。
以下に鎌倉時代の新田系図を示す。
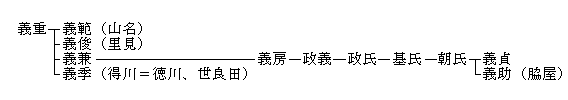
政権が北条氏に代わってからも、新田氏の冷遇は続く。
四代政義は寛元二年(1244)、無断出家の罪を問われて所領の一部を没収され、なおかつ隠居を命じられる。その上、新田の惣領権を召し上げられ、分家の岩松、世良田に新田の家督を譲り渡すという屈辱まで受けている。
六代基氏の時に許されて、再び新田の家督を奪還することができたが、鎌倉方に対する恨みは、恐らく義貞まで受け継がれていたものと推測される。
新田には、足利と違って中央の政争に絡んだ記事も少ない。
3.足利泰氏の失敗、足利家時の自害名将義氏を父に持ち、三代執権北条泰時の甥でもある足利泰氏は、名門の御曹司らしく順調に出世。丹後守、宮内少輔と栄達を重ね、五代執権時頼の妹を正妻に迎えて足利の前途は洋々であるかに思えた。
しかし宝治一年(1247)にその正妻を亡くすと、世をはかなんでか建長三年(1251)に幕府に無断で出家、隠居をしてしまう。
これが北条の逆鱗に触れ、所領の一部は没収、以後足利氏は以前のように、北条氏から全幅の信頼を置かれる事はなくなった。
(ただ、さすがに足利は新田のような酷い扱いは受けていない。足利は北条、安達に次いで有力な御家人で、なおかつ北条に従順であったが為だろうか。罪状は新田政義とおんなじなのにねぇ・・・。)更に二代後の足利家時は、美作国所領を高野山と争い敗訴、義氏以来の所領を失ってしまう。
その後家時は、頼朝より始まった源氏の鎌倉政権が、平氏である北条家に専横されている事に絶望し、自害したと伝えられる。
後世足利一族の今川了俊が「難太平記」で語るには、このとき家時が、「足利が天下を取る」と宣言した置き文を子孫に託し、これを見た孫の尊氏と直義が天下取りを志したという事である。が、とっても嘘くさい。ただ、こういう見方はできるかも知れない。
足利歴代当主は全て北条氏を母に持っているのだが、家時と尊氏&直義のみは側室上杉氏から生まれている。北条の血の薄い当主同士(しかも母方は同じ上杉氏)、世代を超えて通じるものがあったのかも。
母の実家が違えば、裏切りも心理的にやりやすい筈ではないか。家時の不審死の真相は、北条子飼の武将平頼綱と安達泰盛が対立、敗戦した安達氏が滅亡した霜月騒動(1285)に連座したのではないか、との説がある。
いずれにせよ、こういったトラブルが続き、如何に北条と親密だった足利といえども、北条の疑念を振り払うことか難しくなってきた。鎌倉創業以来、頼朝の家系は絶え、梶原、和田、三浦、安達といった有力御家人は全て北条氏に潰された。
気が付けば、次は足利の番じゃないか・・・。
4.北条政権への不満と反乱への下地こうした過程を経て、北条氏に対して、新田は恨みを、足利は不安を抱えていく事になった。
北条氏が強力な間はつけいる隙もなかった両家だが、元寇を期に、水も漏らさぬ筈の北条の政治システムが少しづつ瓦解していく。
再び、平氏の手から源氏の手に政権を、という百年前の意志が両家に湧き上がって来てもおかしくはない。鎌倉幕府崩壊への下地は少しづつではあるが、整えられつつあった。